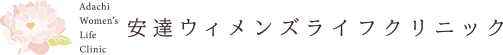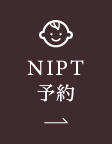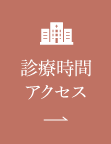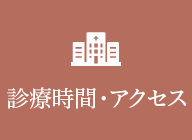今回、産経新聞の記事、出生前診断で「異常なし」、生まれた子はダウン症 30代夫婦が病院に起こした訴訟の行方についての私見を述べたいと思います。
この記事の内容によると、患者様は36歳のオーストラリア国籍の方です。高年妊娠であり、胎児の染色体異常を心配され、「胎児の異常の検査はできますか?」と担当医に相談したようです。医師は超音波検査による胎児の形態・発育から、「異常は見当たらず、ダウン症の特徴はない」とお伝えしたようです。しかしながら、実際生まれてきた子はダウン症候群であり、この患者様は出生前検査の機会を失ったとして病院を提訴したとのことです。
この患者様とは英語でやりとりがなされていたようで、患者様と病院側の主張が異なってるようです。
超音波検査は17週に実施され、その時点で患者様は胎児の染色体異常を調べるgenetic testing (遺伝学的検査)を希望したが、そのための検査 (羊水検査)の提案や情報提供が無かったと主張しています。これに対し、病院側は遺伝学的検査の希望は「聞いていない」とのことで、また、「検査結果は(流産リスクがある)羊水検査を強く勧めるものではない」と伝えていたようです。
恐らく、超音波検査による胎児の首のむくみ (NT: Nucal Translucencyと呼びます。詳細はこちらをご覧ください)の程度と母体年齢から推定されるダウン症候群のリスクはさほど高くなく、羊水検査の合併症で流産する確率 (約1/300)を上回るほどではないから、羊水検査を積極的に勧めなかったということだと思いますし、病院側の主張は間違っていないと思います。
このようなやりとりが全て英語でなされていたとするならば、双方の主張内容がうまく伝わっていなかった可能性があります。もし14週までにgenetic testingの希望を伝えていればNIPTという選択肢があったと思いますが、妊娠17週の段階では難しいのが現状です。
なぜならば、
①NIPTには解析に2週間程度かかり、そこで陽性と判定された場合に、本当に胎児に染色体異常があるかどうかを確認するために羊水検査が必要 (NIPTでは陽性と判定されても、染色体異常細胞が胎盤のみに存在し、胎児には存在せず、胎児は正常な場合があるためです。)
②羊水検査に3週間程度要する
③羊水検査で染色体異常が確定し、妊娠継続を希望しない場合、22週までに人工妊娠中絶が必要
などの要件があるからです。
17週の段階で染色体異常を調べる検査は羊水検査ということになりますが、検査による出血・腹痛・流産などの合併症から、患者様が希望したとしても安易に実施できるものではなく、染色体異常を強く疑う所見や根拠がなければ積極的には勧めないのが現状です。また、首のむくみが見つかったから必ずしもダウン症候群であるとは限りませんし、胎児の発育や形態が一見正常であっても、実はダウン症候群であることもあります。超音波検査のみでは限界があります。そのため、昨今では、比較的妊娠週数の早い段階 (10~14週台)で母体の採血で高精度にダウン症候群の可能性を評価するNIPTが増加傾向にあります。
「胎児に先天的な病気や障害がないか心配だから、あらかじめ調べたい」という患者様のお気持ちは重々理解できますし、そのために実施可能な検査とその時期、検査の精度・限界・対象となる疾患の特徴などを正しく伝えるための知識やノウハウを、本来は全ての産婦人科医師が備えるべきではあります。しかしながら、実際には専門的な知識と経験が必要ですし、ましてや今回のように英語でコミュニケーションするのは相当大変であったかと思います。それらの対応可能な臨床遺伝専門医が在籍し、一定の要件を満たした医療機関がNIPT認証施設として定められております。
この患者様方が出生前検査に関して知識を持ち、もう少し早い段階でNIPT認証施設で相談していれば、結果は違っていたかもしれません。
今回の訴訟は地裁では病院側の内容を認めたようですが、不服として高裁へ控訴するようです。今回の訴訟について今後の動向を注視したいと思います。