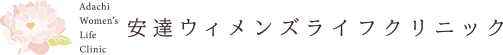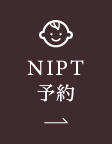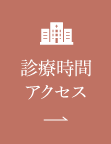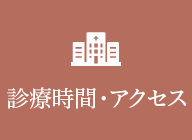今回、毎日新聞の記事、無認証施設で「陽性」と告げられてー出生前検査をめぐる夫婦の葛藤と決断の記事についての私見を述べたいと思います。
この記事の内容によると、患者様は出生前診断 (NIPT)の認可外施設で検査を受け、クラインフェルター症候群の陽性反応が出たとのことで、検査を受けた施設では適切な事後対応がなされず、かかりつけ先の産院で相談することから始まります。
かかりつけの産院では確定診断(羊水検査)を行っていないため、大学病院を紹介されますが、認可外施設でNIPTを受けたこと、(羊水検査の結果次第での)中絶は対応していないから別の病院に行くようにと、高圧的な対応をされたようです。
認可外施設でNIPTを受けたことに担当医が激高したとのことですが、確かに認可外施設で適切な説明やカウンセリングを経ずに検査を受けたことに伴い、その後の事後対応をしなければならないことで怒りをあらわにしたことについては、ある程度理解できます。しかしながら、怒りの矛先が患者様に向かうのは果たしていかがなものでしょうか?「授かった赤ちゃんに障害がないか知りたい、五体満足で生まれてきて欲しいから出生前診断を受けたい」という患者様とそのご家族の権利はごく自然なものだと思います。全ての患者様がNIPTの施設認定制度について把握してるわけではありません。総じて、認可外施設は誇大広告する傾向にあるため、そちらで検査を受ける方が一定数いらっしゃるのも事実です。「おなかの赤ちゃんのために」と思って検査を受けただけなのに、なぜ叱責されないといけないのか・・・患者様とそのご家族の悲しさと悔しさが伝わってくる内容でした。
結果として、ご夫婦は羊水検査を受けず出産する選択をされたようです。生まれた子はクラインフェルター症候群でした。
性別を決定づける性染色体にはX染色体とY染色体があり、女性はX染色体を2本、男性はXとYの染色体を1本ずつ有しますが、クラインフェルター症候群では、X染色体を2本、Y染色体を1本有することで、男性として生まれてきますが、思春期以降の2次性徴において、性機能や精子形成に影響し、男性不妊の原因になります。治療法は主に男性ホルモンの補充療法になります。
ご夫婦はNIPTを受けたことでクラインフェルター症候群と診断されたお子さんに対し、心の準備ができ、子育てについても前向きに捉えられるようになったそうですが、中には認可外施設のNIPTでクラインフェルター症候群の可能性があるとされ、結果として中絶した事例もあるようです。
クラインフェルター症候群をはじめ、性染色体に変化を伴うことをDSD(Differences of Sex Development)と呼びます。他にはターナー症候群をはじめ、アンドロゲン不応症や副腎不全などが含まれます。症状の出方や程度は個々によって差があり、一人の人間として社会生活を送っておられる方もおります。DSDを一概に、先天的な「病気」「障害」と捉えるべきではありません。(詳細はこちらもご参照ください。)DSDに対する正確な理解もなく、漫然と性染色体について出生前診断の検査対象とすることは人権侵害につながりかねませんし、NIPTの認可施設ではこれらを検査対象としておりません。
「胎児に先天的な病気や障害がないか心配だから、あらかじめ調べたい」という患者様のお気持ちは重々理解できますが、漫然とDSDについても評価するのは好ましくないと思います。予約なしで休日でも検査可能な認可外施設は患者様にとって便利だとは思いますが、本来であれば臨床遺伝専門医の資格を有する産婦人科医や小児科医が在籍する専門的な医療機関で相談すべきだと思います。
クラインフェルター症候群などの当事者や家族をサポートしている、日本性分化疾患患者家族会連絡会(ネクスDSDジャパン)は、性染色体を対象にしたNIPTが広まることを懸念し、NIPT認可外施設での性染色体検査について要望書を提出し、NIPTの認可外施設に対する法的規制を求めたとのことで、今後の動向を注視したいと思います。